
なぜ北極星は変わるのか? 歳差運動と地球の動き
夜空を見上げると、北斗七星とともにいつも変わらず輝いているように見えるのが「北極星」です。
しかし実は、未来の北極星は今の星とは異なることをご存じでしょうか?
地球の歳差運動とは?
地球は自転しながら、コマのように自転軸がゆっくりと首振り運動をしています。これを「歳差運動(さいさうんどう)」と呼びます。
歳差運動によって、地球の自転軸の延長線が天球上で円を描くように動き、約25,700~25,800年かけて一周します。そのため、天の北極に最も近い「北極星」は、数千年ごとに別の星へと交代していくのです。
過去・現在・未来の北極星
現在の北極星は「こぐま座α星(ポラリス)」で、北極からわずか0.7度程度の位置にあり、航海や方角確認の基準として利用されています。
過去には、紀元前3000年頃に「りゅう座のトゥバン(α星)」が北極星として機能していました。
そして未来には、こと座の「ベガ(Vega)」が北極星に近づく時代が訪れます。その時期はおよそ西暦14,000年頃と推定されており、約12,000年後という見積もりもあります。
私たちの人生スパンではほとんど変わらない夜空も、地球規模の時間軸では常に変化しているのです。
地球は常に動いている
星空だけでなく、私たちの足元にある地球もまた絶えず動き続けています。
自転や歳差運動に加え、プレートの移動による大陸移動、地殻の隆起・沈降などが日々進行しています。
このため、正確な位置情報や標高データを常に最新化し、地球の変化を反映することが重要です。日本では2024年に「標高モデル測地成果2024」が導入され、最新の地形変動を反映した測地成果が提供されています。私たちは、「標高モデル測地成果2024」モデルへ改定された今、高さの動きに注視しながら、位置情報を持続可能な手法で取得し管理することが必要だと考えています。
なぜ海底地形を記録することが重要なのか?
まとめ
いつも変わらないように見える北極星も、長い時間の流れの中では別の星へと交代していきます。
同じように、地球もまた絶えず変化を続けています。
宇宙と地球のダイナミックな動きを理解し、その変化に対応することは、未来の社会や環境と共生するうえで欠かせない視点といえるでしょう。
―― ちなみに、こと座のベガが北極星に最も近づくのは西暦14,000年頃。
その未来の星空を想像してみるのも、ロマンのある楽しみ方かもしれません。
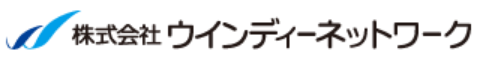

.jpg)

